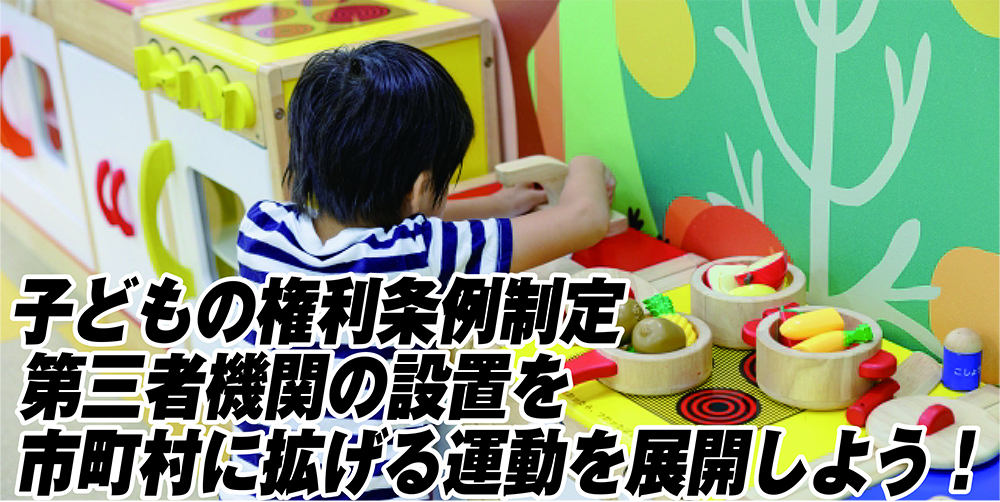子どもの権利条例制定・第三者機関の設置を市町村に拡げる運動を展開しよう!
11月20日は、子どもの基本的人権を国際的に保障すると定めた「子どもの権利条約」(児童の権利に関する条約)の採択(1989年11月20日)を記念した「世界こどもの日」です。今年は日本の条約批准から30年になります。
全国で約50の自治体が独自の条例に基づき、子どもの人権問題に対応する第三者機関を設置しています。第三者機関は2023年度、家庭問題や学校問題など計8千件の相談を受けており、行政に勧告や提言する例もあります。
「第三者機関の設置、さらに広がる可能性」
第三者機関は各自治体の条例に基づいて設置され、「子どもの相談・救済機関」などと呼ばれています。司法関係や教育関係などの専門家数人が、相談や調査にあたるスタッフと活動し、関係機関や自治体に対して調査・勧告・提言する権限を持つことが多いのです。第三者機関の活動は、政府も支援する姿勢を示していることから、第三者機関の設置がさらに広がる可能性もあります。
「兵庫県川西市を皮切りに広がった」
 第三者機関は、2022年6月に「こども基本法」が成立した以降、11の自治体が設置するなど2割以上増えました。
第三者機関は、2022年6月に「こども基本法」が成立した以降、11の自治体が設置するなど2割以上増えました。
2024年5月時点の第三者機関を設置している自治体は、埼玉、長野、山梨、秋田の4県や札幌、相模原、名古屋、川崎、新潟の5政令指定都市など52自治体と、福岡県志免町など8町です。
国連NGO「子どもの権利条約総合研究所」によると、第三者機関は1998年に条例を制定した兵庫県川西市を皮切りに広がったとのことです。
「子どもは自分に起きていることを人権侵害と意識しないことが多い」
朝日新聞のアンケート(24.11.20.朝刊)では、回答のあった49機関が2023年度に受けた相談は約計8065件で、そのうち2863件は子どもから。相談内容は「子育ての悩み」「子ども同士の交友関係」「家庭環境や家族関係」など、幅広い分野に及んでおり、当事者の子と面会した回数は1091回だったと記されています。
 国連NGO「子どもの権利条約総合研究所」副代表の野村武司・東京経済大学教授(子ども法)は、相談内容の多様さについて、「どんな相談も拒まない第三者機関が多い」ためと指摘し、「子どもは自分に起きていることを人権侵害と意識しないことが多い。専門家が丁寧に話を聞き、人権の問題がないか見極め、一緒に解決策を探るのが大切」と意義を語っていると報道されています。
国連NGO「子どもの権利条約総合研究所」副代表の野村武司・東京経済大学教授(子ども法)は、相談内容の多様さについて、「どんな相談も拒まない第三者機関が多い」ためと指摘し、「子どもは自分に起きていることを人権侵害と意識しないことが多い。専門家が丁寧に話を聞き、人権の問題がないか見極め、一緒に解決策を探るのが大切」と意義を語っていると報道されています。
「子どもの権利相談室『なごもっか』」
子どもの権利のために活動する第三者機関を開設する自治体が、少しずつ増えていることから、親身な相談対応の結果、実際に行政を動かした例もあります。
2022年7月、名古屋市立高校の体育館で、高さ8メートルの位置にある窓ガラスが突然割れ落ちる事故がありました。幸い負傷者はなかったのですが、築約60年の校舎では、2ヶ月前に外壁が剥がれ落ちる事故も起きていました。
当時、名古屋市立高校の2年生だった女性は、学校側に再発防止策を訴えましたが、動きが鈍く感じたことで、「命を守るために何かしなくては」と、改修に必要な手続きを自分で調べ始めました。そんなとき、両親から「子どもの権利相談室『なごもっか』」の存在を聞いたのです。
「なごもっか」は、条例に基づく第三者機関です。2023年度は418件の相談を受け、学校や家庭、勉強や健康の話しなど幅広い内容で、必要に応じて調査や勧告、提言もします。
「校舎改修の訴えが、第三者機関を通して実現した」
「子どもの権利の視点で意見を聞きたい」と思った名古屋市立高校の女性は、どこまで応じてくれるか不安もありましたが、相談員は「一緒に解決しよう」と言い、ともに学校や市教育委員会の担当者と協議を重ね、河村たかし市長(当時)とも面談しました。そして、2023年度末に154万円をかけ、窓の飛散防止フィルムと防護ネットを付ける工事が実現したのです。
 なごもっか委員の川口洋誉(ひろたか)・愛知工業大学准教授(教育行政学)は「学校は子どもたちのためにあるのに、校舎や設備について、子どもの意見はほぼ聞かれない。貴重な事例だった」と話しました。市教育委員会の担当者は「こちらの事情や思いを子どもにどう伝えたらいいのか悩むこともあるので、『なごもっか』が話し合いの場に入ってくれてよかった」と言いました。
なごもっか委員の川口洋誉(ひろたか)・愛知工業大学准教授(教育行政学)は「学校は子どもたちのためにあるのに、校舎や設備について、子どもの意見はほぼ聞かれない。貴重な事例だった」と話しました。市教育委員会の担当者は「こちらの事情や思いを子どもにどう伝えたらいいのか悩むこともあるので、『なごもっか』が話し合いの場に入ってくれてよかった」と言いました。
名古屋市立高校の女性は「相談する前は一人で闘うしかないと思っていた。圧倒的な力の前にくじけそうな子どもにとって力になってくれる組織だと思う」と話しました。
「尼崎市の第三者機関が、市に改善を要求」
「なごもっか」のように、自治体の条例に基づいて設置される第三者機関は「子どもの相談・救済機関」と呼ばれています。個別事案の対応だけではなく、自治体の施策を提言する機関もあります。
 兵庫県尼崎市の第三者機関は2023年、保育所入所に関する市の対応が「差別状況」だと指摘しました。ある保育所が、障害がある子を断ったのに、市のホームページでは空き情報を「△」として募集を続けていたからです。
兵庫県尼崎市の第三者機関は2023年、保育所入所に関する市の対応が「差別状況」だと指摘しました。ある保育所が、障害がある子を断ったのに、市のホームページでは空き情報を「△」として募集を続けていたからです。
第三者機関の調査に対し、尼崎市は、「支援が必要な子どもの場合、態勢が整わず、空きがあっても入所に結びつかない場合がある」と説明しましたが、第三者機関は、情報発信の改善や保育士不足の解消など求めたことから、尼崎市は改善策を検討しています。
「第三者機関の設置の課題」
第三者機関の設置は約50自治体です。朝日新聞のアンケート(24.11.20.朝刊)では、第三者機関の設置の課題として、「スタッフの確保」(31機関)、「認知度が低い」(26機関)、「委員となる有識者の確保」(23機関)などが挙がっています。また、「設置自治体が増えると人材確保が困難になる」という懸念もありました。
こうした第三者機関の設置について、政府は「こども大綱」で、実態把握や周知、活動支援をするとしていますが、朝日新聞のアンケートでは「全ての子どもが救済を受けられるように」「自治体の機関には限界がある」などの理由で、国レベルの第三者機関設置を求める意見も多くありました。
「子どものコミッショナー」
 公益財団法人・日本ユニセフ協会によると、国レベルの第三者機関設置は「子どものコミッショナー」などと呼ばれ、2012年時点で、世界70ヵ国以上が設置しています。その働きかけで、イギリスのスコットランドでは「体罰禁止の法律」ができたり、フィンランドでは「児童養護施設を出た後の支援を25歳まで延長する法改正」が実現しています。
公益財団法人・日本ユニセフ協会によると、国レベルの第三者機関設置は「子どものコミッショナー」などと呼ばれ、2012年時点で、世界70ヵ国以上が設置しています。その働きかけで、イギリスのスコットランドでは「体罰禁止の法律」ができたり、フィンランドでは「児童養護施設を出た後の支援を25歳まで延長する法改正」が実現しています。
日本ユニセフ協会広報・アドボカシー推進室長の中井裕真さんは「日本には子どもの目線に立って政策を監視する独立した公的機関がない。地方レベルでできないことを担保するためにも子どもコミッショナーは必要だ」と話しました。
私たち労働組合は人権擁護団体でもあります。人権を学び、その学んだことを実践することが求められています。
国連子どもの権利条約に基づく、子どもの権利条例・第三者機関の設置を市町村に拡げる運動を展開しましょう!
第4回 人権問題シンポジウム 開催!

日 時:2024年12月7日 15:00~17:00
場 所:エルおおさか南館7階 南734
講 師:秋田 真志弁護士 テーマ:プレサンス元社長冤罪事件における
権力犯罪と人質司法
~取り調べ可視化が浮かび上がらせた
日本の刑事司法の闇~
資料代:500円
お問合せ:連帯ユニオン人権部 担当:武谷 新吾
TEL:06-6583-5546
 労働組合活動を犯罪扱いさせてはなりません
労働組合活動を犯罪扱いさせてはなりません「京都事件」は、ベスト・ライナー、近畿生コン、加茂生コンの3つの事件(労働争議)を併合審理する刑事裁判です。労働争議の解決金を受領したことが「恐喝」とされています。
争議解決にあたって、会社側に解雇期間中の未払い賃金、雇用保障、組合の闘争費用などを解決金として支払わせることは、裁判所や労働委員会でも当然の実務として定着しています。ところが、警察・検察は、関生支部は労働組合を名乗る反社会勢力で、金銭目当てで活動してきたそんなストーリーで前代未聞の事件を仕組んだのです。
企業の団結権侵害に対する抗議行動や団体行動を犯罪扱いする警察・検察の暴挙を許せば、憲法28条が保障した労働基本権がなかった時代への逆戻りです。裁判所は毅然たる姿勢で無罪判決を出すべきです。すべての労働組合のみなさまに署名活動へのご協力をよびかけます。
署名活動の実施要領
提 出 先:京都地方裁判所第2刑事部
署名の種類:団体署名を実施します(個人署名ではありません)
署名用紙は、 ココをクリック
集約と提出:第1次集約 9月末日(10月中旬提出)
第2次集役 10月末日(11月中旬提出)
最終週役 11月末日(12月中旬提出)
送 り 先:〒101ー0062
東京都千代田区神田駿河台3ー2ー11 連合会館
フォーラム平和・人権・環境気付
関西生コンを支援する会 ホームページ ココをクリック
TEL:03ー5289ー8222
【竹信三恵子のホントの話】
 デモクラシータイムスで、「関西生コン事件」の解説。刑事裁判で無罪になった二人の組合員と、組合員を雇った、組合員に仕事を出したことを背景にセメントの販売を拒絶され兵糧攻めにあっているセメント製造業者をインタビュー。また、「産業別労働組合」の歴史の経過を詳しく解説。
デモクラシータイムスで、「関西生コン事件」の解説。刑事裁判で無罪になった二人の組合員と、組合員を雇った、組合員に仕事を出したことを背景にセメントの販売を拒絶され兵糧攻めにあっているセメント製造業者をインタビュー。また、「産業別労働組合」の歴史の経過を詳しく解説。動画閲覧できます ココをクリック
ドキュメンタリー番組の前に放送されたMBSラジオ「関西生コン事件とは何か」がネットで聞けるようになりました。
以下のところから聞くことができます。
▼Spotify ココをクリック
▼Apple ココをクリック
▼Amazon ココをクリック
関生弾圧について家族の目から描いた『ここから~「関西生コン事件」と私たち』が5月10日、2023年日隅一雄・情報流通促進賞奨励賞に選出されました。詳しくはコチラ ココをクリック
第26回ソウル人権映画祭で上映されました。 ココをクリック
6月13日から開催される、第26回ソウル人権映画祭(ソウルマロニエ公園一帯)。
14日(金)に『ここから「関西生コン事件」とわたしたち』が上映されます。英語・韓国語・字幕、韓国手話付き。全22作品を上映。
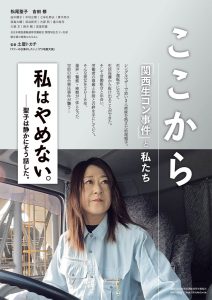 映画 ここから 「関西生コン事件」と私たち
映画 ここから 「関西生コン事件」と私たち
この映画は「フツーの仕事がしたい」「アリ地獄天国」など労働問題を取り上げ注目を浴びている土屋トカチ監督の最新作。「関西生コン事件」の渦中にある組合員たちの姿を描いた待望のドキュメンタリー映画『ここから「関西生コン事件」と私たち』がこのほど完成。業界・警察・検察が一体となった空前の労働組合潰しに直面した組合員と家族の物語を見つめた。(左写真は松尾聖子さん)いまも各地で上映会がひらかれている。
お問い合わせはコチラ ココをクリック
ー 公判予定 ー
| 12月はありません |
|---|