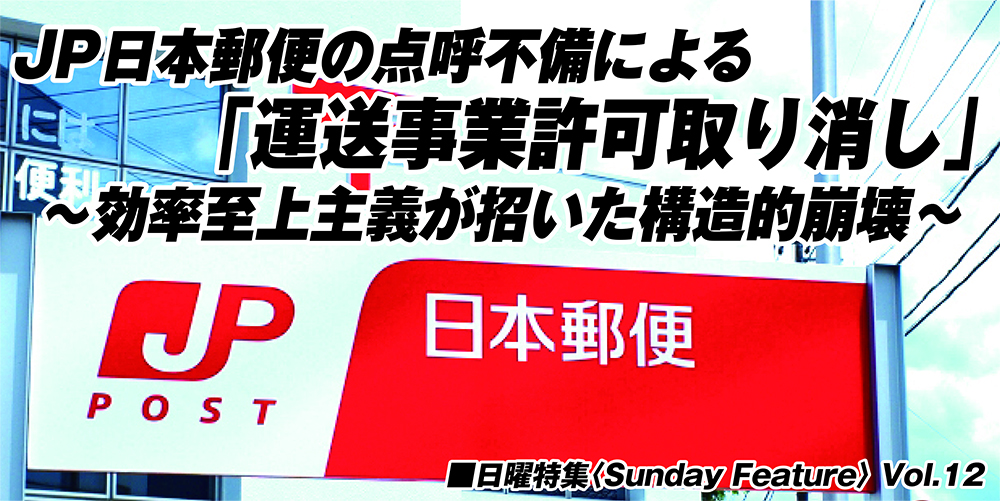JP 日本郵便の点呼不備による「運送事業許可取り消し」
~効率至上主義が招いた構造的崩壊~
日本郵便の運行管理不備に関する一連の事態は、単なる現場の業務過失という次元を超え、市場原理主義がもたらした民営化の負の影響が明白に露呈した、深刻な構造的問題をはらんでいます。
「全国に蔓延した法令違反と最も重い行政処分」
 この問題は、郵政事業を支える労働者の人権やキャリア、そして組織の将来そのものを根底から揺るがすものです。現在講じられている車両制限や民間委託の拡大といった対策は、突き詰めれば対症療法に過ぎず、「効率至上主義」の名の下で、現場の労働者には安全・健康の危機と雇用の空洞化という二重の重圧がのしかかっています。この問題の規模と深刻さは、国土交通省が下した行政処分の重さによって裏付けられています。全国3,188局の調査において、実に約75%にあたる2,391局で運転者への点呼などの安全確認に不備が確認され、不適切な点呼はのべ15万件に上ると報じられました。これを受け、国交省はトラックなど約2,500台分の運送事業許可を取り消すという、事業停止処分を遥かに超える最も重い行政処分の方針を固めました。これは、組織内部で本来機能すべき「安全文化」が全国レベルで崩壊していた事実を証明するものであり、民営化以降に加速した「ルールよりも納期・効率優先」という無言の圧力が、労働者の命と健康を軽視する姿勢の明確な表れであったと言えます。
この問題は、郵政事業を支える労働者の人権やキャリア、そして組織の将来そのものを根底から揺るがすものです。現在講じられている車両制限や民間委託の拡大といった対策は、突き詰めれば対症療法に過ぎず、「効率至上主義」の名の下で、現場の労働者には安全・健康の危機と雇用の空洞化という二重の重圧がのしかかっています。この問題の規模と深刻さは、国土交通省が下した行政処分の重さによって裏付けられています。全国3,188局の調査において、実に約75%にあたる2,391局で運転者への点呼などの安全確認に不備が確認され、不適切な点呼はのべ15万件に上ると報じられました。これを受け、国交省はトラックなど約2,500台分の運送事業許可を取り消すという、事業停止処分を遥かに超える最も重い行政処分の方針を固めました。これは、組織内部で本来機能すべき「安全文化」が全国レベルで崩壊していた事実を証明するものであり、民営化以降に加速した「ルールよりも納期・効率優先」という無言の圧力が、労働者の命と健康を軽視する姿勢の明確な表れであったと言えます。
「組織的無責任が招く「安全配慮義務の形骸化」」
 運行管理、特に点呼などの基本的な安全確認の形骸化は、企業が負うべき労働者への安全配慮義務の重大な欠如にほかなりません。車両不足によって集配ルートが非効率化し、長時間労働や休憩時間の削減が常態化すれば、職員は疲労困憊の状態でハンドルを握らざるを得なくなります。形だけの点呼が横行していたなら、企業は職員の過労運転のリスクを意図的に見過ごしていたに等しく、その根底には「ルールよりも納期・効率優先」という組織の無言の圧力があった可能性が高いです。このような環境では、現場職員は問題を報告するよりも、無理をしてでも業務を遂行することを強いられ、精神的なプレッシャーが増す一方で、組織的な安全体制は絵に描いた餅と化します。
運行管理、特に点呼などの基本的な安全確認の形骸化は、企業が負うべき労働者への安全配慮義務の重大な欠如にほかなりません。車両不足によって集配ルートが非効率化し、長時間労働や休憩時間の削減が常態化すれば、職員は疲労困憊の状態でハンドルを握らざるを得なくなります。形だけの点呼が横行していたなら、企業は職員の過労運転のリスクを意図的に見過ごしていたに等しく、その根底には「ルールよりも納期・効率優先」という組織の無言の圧力があった可能性が高いです。このような環境では、現場職員は問題を報告するよりも、無理をしてでも業務を遂行することを強いられ、精神的なプレッシャーが増す一方で、組織的な安全体制は絵に描いた餅と化します。
「民間委託の拡大がもたらす「雇用の空洞化とキャリアの閉塞」」
 車両不足を補うための民間委託の拡大は、現場労働者のキャリアを直接的に脅かし、郵政事業の根幹を揺るがす長期的なリスクを抱えています。業務が外部委託されることで、職員が経験を通じて習得すべき複雑なルート構築、特殊荷物の取り扱い、顧客との機微なコミュニケーションといった貴重なノウハウやスキルが組織外に流出し、現場職員の役割が単なる「荷物の引き渡し担当者」に限定されてしまいます。これにより、将来的に運行管理者やエリアマネージャーといったキャリアアップの道筋が細ってしまう恐れが生じます。また、「自分の仕事が外部の低コストな労働力に置き換えられるかもしれない」という不安は「雇用の空洞化」への懸念となり、極めて大きなモチベーション低下につながり、優秀な人材の離職率増加を招きかねません。
車両不足を補うための民間委託の拡大は、現場労働者のキャリアを直接的に脅かし、郵政事業の根幹を揺るがす長期的なリスクを抱えています。業務が外部委託されることで、職員が経験を通じて習得すべき複雑なルート構築、特殊荷物の取り扱い、顧客との機微なコミュニケーションといった貴重なノウハウやスキルが組織外に流出し、現場職員の役割が単なる「荷物の引き渡し担当者」に限定されてしまいます。これにより、将来的に運行管理者やエリアマネージャーといったキャリアアップの道筋が細ってしまう恐れが生じます。また、「自分の仕事が外部の低コストな労働力に置き換えられるかもしれない」という不安は「雇用の空洞化」への懸念となり、極めて大きなモチベーション低下につながり、優秀な人材の離職率増加を招きかねません。
「負の波及効果 不公平な評価と待遇改善の停滞」
 運行管理の不備と業務の混乱は、最終的に労働者の賃金や人事評価といった待遇面にまで負の波及効果をもたらします。車両制限や委託の増加によって、混乱地域で働く職員は非効率な労働を強いられながらも、影響の少ない地域の職員は定常業務をこなせるという業務負荷の地域格差が発生します。結果として、同じ努力をしているにもかかわらず、トラブル対応や残業増加に追われた職員の評価が、かえって下がるという不公平な人事評価が生じる懸念があります。さらに、行政処分による罰金や大規模な委託費用は会社の財政的な負担を増大させ、本来、労働環境の改善(賃上げ、人員補充、設備の更新など)に充てられるべき財源が圧迫されます。これは、不備の尻拭いをさせられている労働者自身の待遇改善が後回しになるという、最も理不尽な結果を招きかねません。
運行管理の不備と業務の混乱は、最終的に労働者の賃金や人事評価といった待遇面にまで負の波及効果をもたらします。車両制限や委託の増加によって、混乱地域で働く職員は非効率な労働を強いられながらも、影響の少ない地域の職員は定常業務をこなせるという業務負荷の地域格差が発生します。結果として、同じ努力をしているにもかかわらず、トラブル対応や残業増加に追われた職員の評価が、かえって下がるという不公平な人事評価が生じる懸念があります。さらに、行政処分による罰金や大規模な委託費用は会社の財政的な負担を増大させ、本来、労働環境の改善(賃上げ、人員補充、設備の更新など)に充てられるべき財源が圧迫されます。これは、不備の尻拭いをさせられている労働者自身の待遇改善が後回しになるという、最も理不尽な結果を招きかねません。
「労働者の犠牲の上に成り立つサービスの限界」
運行管理の不備から始まったこの問題は、組織ガバナンスの欠如が、現場の労働者の人権、キャリア、そして生活にまで深刻な犠牲を強いている構造を浮き彫りにしています。労働者の犠牲の上に無理に業務を維持しようとする姿勢は持続可能性を欠いています。企業は、車両確保や委託業者増加という対症療法ではなく、まず安全ルールを遵守できるだけの余裕を持った人員配置を行い、現場の声を吸い上げるガバナンス体制を再構築することが不可欠です。今こそ、労働者を単なるコストや道具としてではなく、事業の最も重要な担い手として再評価する経営の転換が強く求められています。
真相はこれだ!関生事件 無罪判決!【竹信三恵子の信じられないホントの話】20250411【デモクラシータイムス】
 ご存じですか、「関西生コン」事件。3月には、組合の委員長に対して懲役10年の求刑がされていた事件で京都地裁で完全無罪判決が出ました。無罪判決を獲得した湯川委員長と弁護人をお呼びして、竹信三恵子が事件の真相と2018年からの一連の組合弾圧事件の背景を深堀します。 今でも、「関西生コン事件」は、先鋭な、あるいは乱暴な労働組合が強面の不法な交渉をして逮捕された事件、と思っておられる方も多いようです。しかしそうではありません。企業横断的な「産別組合」が憲法上の労働基本権を行使しただけで、正当な交渉や職場環境の改善運動だったから、強要や恐喝など刑事事件には当たらないものでした。裁判所の判断もこの点を明確にしています。では、なぜ暴力的組合の非行であるかのように喧伝され、関西全域の警察と検察が組織的に刑事事件化することになったのか、その大きな背景にも興味は尽きません。 tansaのサイトに組合員お一人お一人のインタビューも連載されています。ぜひ、どんな顔をもった、どんな人生を歩んできた人たちが、濡れ衣を着せられ逮捕勾留されて裁判の法廷に引き出されたのかも知っていただきたいと思います。
ご存じですか、「関西生コン」事件。3月には、組合の委員長に対して懲役10年の求刑がされていた事件で京都地裁で完全無罪判決が出ました。無罪判決を獲得した湯川委員長と弁護人をお呼びして、竹信三恵子が事件の真相と2018年からの一連の組合弾圧事件の背景を深堀します。 今でも、「関西生コン事件」は、先鋭な、あるいは乱暴な労働組合が強面の不法な交渉をして逮捕された事件、と思っておられる方も多いようです。しかしそうではありません。企業横断的な「産別組合」が憲法上の労働基本権を行使しただけで、正当な交渉や職場環境の改善運動だったから、強要や恐喝など刑事事件には当たらないものでした。裁判所の判断もこの点を明確にしています。では、なぜ暴力的組合の非行であるかのように喧伝され、関西全域の警察と検察が組織的に刑事事件化することになったのか、その大きな背景にも興味は尽きません。 tansaのサイトに組合員お一人お一人のインタビューも連載されています。ぜひ、どんな顔をもった、どんな人生を歩んできた人たちが、濡れ衣を着せられ逮捕勾留されて裁判の法廷に引き出されたのかも知っていただきたいと思います。
動画閲覧できます ココをクリック
増補版 賃金破壊――労働運動を「犯罪」にする国
勝利判決が続く一方で新たな弾圧も――
朝⽇新聞、東京新聞に書評が載り話題となった書籍の増補版!関生事件のその後について「補章」を加筆。
1997年以降、賃金が下がり続けている先進国は日本だけだ。そんな中、関西生コン労組は、労組の活動を通じて、賃上げも、残業規制も、シングルマザーの経済的自立という「女性活躍」も、実現した。そこへヘイト集団が妨害を加え、そして警察が弾圧に乗り出した。
なぜいま、憲法や労働組合法を無視した組合潰しが行なわれているのか。迫真のルポでその真実を明らかにする。初版は2021年。本書はその後を加筆した増補版である。
◆主な目次
はじめに――増補にあたって
プロローグ
第1章 「賃金が上がらない国」の底で
第2章 労働運動が「犯罪」になった日
第3章 ヘイトの次に警察が来た
第4章 労働分野の解釈改憲
第5章 経営側は何を恐れたのか
第6章 影の主役としてのメディア
第7章 労働者が国を訴えた日
エピローグ
補章 反攻の始まり
増補版おわりに
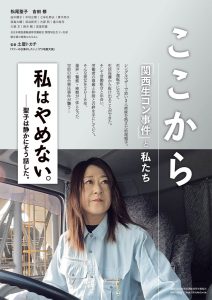 映画 ここから 「関西生コン事件」と私たち
映画 ここから 「関西生コン事件」と私たちこの映画は「フツーの仕事がしたい」「アリ地獄天国」など労働問題を取り上げ注目を浴びている土屋トカチ監督の最新作。「関西生コン事件」の渦中にある組合員たちの姿を描いた待望のドキュメンタリー映画『ここから「関西生コン事件」と私たち』がこのほど完成。業界・警察・検察が一体となった空前の労働組合潰しに直面した組合員と家族の物語を見つめた。(左写真は松尾聖子さん)いまも各地で上映会がひらかれているお問い合わせはコチラ ココをクリック
ー 公判予定 ー
| 11月18日 大津第2次事件 大阪高裁(判決) |
14:30~ |
|---|